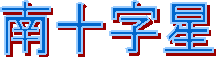 part2 part2 |
*2006年6月20日(火)第4号* JICA SV 加藤眞理 今月はCOPAで世界中が沸いています。ブラジルは、優勝して当たり 前で、国民の関心は得点と試合内容だけにあるようです。 試合ごとに一喜一憂する国から来た私は驚いています。 |
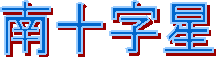 part2 part2 |
*2006年6月20日(火)第4号* JICA SV 加藤眞理 今月はCOPAで世界中が沸いています。ブラジルは、優勝して当たり 前で、国民の関心は得点と試合内容だけにあるようです。 試合ごとに一喜一憂する国から来た私は驚いています。 |
|
第139回定例会開催さる
6月3日(土)、サン・ミゲル・アルカンジョにて行われた第139回定例会は、第1講でピラール・ド・スールの押見先生がパソコンの授業例を紹介して下さいました。ブラインド・タッチの練習の仕方は、沢山の先生方にも参考になると思います。
第2講では、ヴァルゼン・グランデの森谷先生が移民の授業例を紹介してくれました。森谷先生は、去年から週1回の移民の授業を継続して行い、その集大成を8月の学芸会で発表するという事でした。最初に父兄の協力を 仰ぎ、父兄、生徒、教師が協力して進めてきた授業です。各校でも、色々と対策を立てていると思いますが、森谷先生の授業例を参考にして、移民の授業を検討してみて下さい。
役員からの質問
6月は、次期青年要請申請期です。この機会に、各文協、各校で青年ボランティアを要請する目的を再度確認してみましょう。
先日、ある役員から「先生たち日本からいらした人は、地元教師のスキルアップのために来たと仰るけど、そういうことを言ったら、地元の教師は辞めてしまいますよ」と言われました。多分、殆どの役員が同じことを考えていらっしゃると思います。でも、日本から来たボランティアは、地元の先生達に難しい事を教えに来たわけではないのです。日本語を、なるべくわかりやすく生徒に教えるコツを地元の先生達に伝えに来ているのです。
青年ボランティアは、地元の教師の代替教師ではありません。日本で、特別に日本語の教え方を学んできています。そのテクニックを学んで下さい。また、青年ボランティアは、自分が養成校などで日本語の教え方を学んだ時の「目からうろこが落ちた」新鮮な経験を、是非、丁寧に地元の教師に教えて下さい。時には、色々と摩擦も生じるでしょうけれど、摩擦が生じて当然だと思います。 ブラジルへ来るまで、日系社会で日本語を学ぶ事がこんなにも大変なことだとは思いませんでした。
|
二世の方でさえも、大変な苦労をして日本語を学んでいるという現状を、正確に把握していませんでした。こういう環境の中で日本語を習得しようとしている三世、四世の生徒達に、少しでもわかり易く色々と工夫して日本語を教えることはとても大切な事です。地元の先生は、単に問題の答えを教えるのでなく、考え方や自分で考えるテクニック、生徒に自分で気付かせるコツを青年ボランティアから学んで下さい。 パソコンのテクニックも同様に学んで下さい。もし仮に、この先、青年ボランティアの派遣が年々減少するとしたら、これまでに培って来た聖南西教育研究会の勉強会や沢山の年間行事の開催は、かなり困難になると思います。せっかくこれまでに地元の諸先輩が、大変な苦労をして築いてきた全てのことも、先生達にしっかり根付いていないと、あっという間に消滅してしまうと思います。
第139回定例会がサン・ミゲルで開催された時に同校の先生方が、学校を綺麗に飾って下さっていました。その中で、他校の先生達の目をひときわ引いたのが、写真のCOPA君でした。このCOPA君、現在、他校に増殖中です。ソロカバではサッカーボールも作りました。当初は、聖南西の各校にもプレゼントしようと思っていたのですが難易度がかなり高いので諦めました。残念!
↑ カッポンのCOPA君 ↑ ソロカバのCOPA君
|